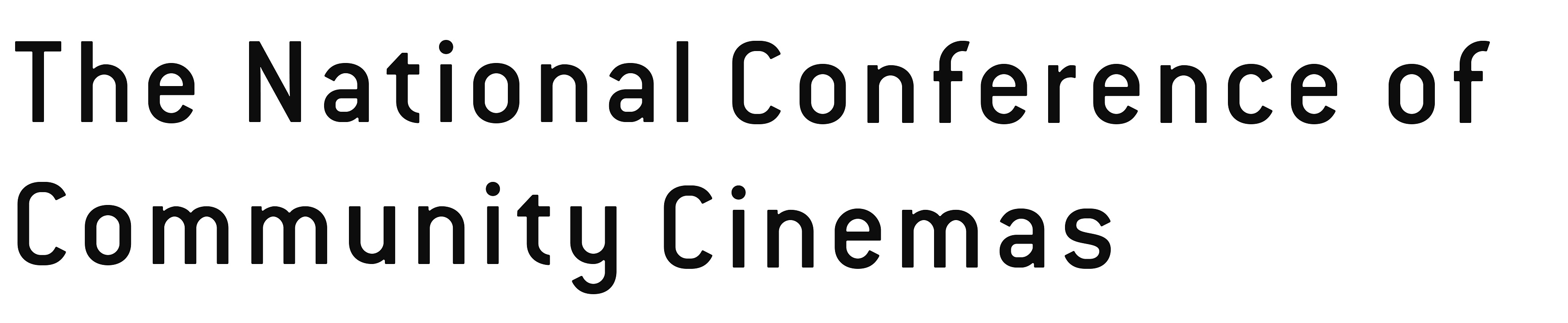
![]()
全国各地で映画上映を行っている人たちの情報交換と研究報告、そしてディスカッション、交流の場として、1996年から毎年開催しています。全国の映画館や、映画祭、シネマテークや公共ホール、シネクラブ、自主上映団体、配給会社、映画や文化政策を学ぶ学生等々、コミュニティシネマの活動に関心のある人たちが集まります。海外のコミュニティシネマ関係者をゲストとして招くこともあります。上映活動を行う人たちが、ネットワークを広げるための大切な場となっています。興味のある方なら誰でも参加できます。
全国コミュニティシネマ会議2023イン高崎
今年の会議は、高崎市で開催します。コロナ禍の3年間を経て、映画館・上映者にも変化が求められています。今年の会議では、危機を乗り越える新しい時代の上映のあり方を考えます。
今年も、“映画上映の現在”を知り、これからの映画上映を豊かにするための、多彩なプログラムを準備しています。
◎プログラム
※出演者等は変更になる場合がございます。ご了承ください。
2023年9月22日[金]
会場:高崎芸術劇場スタジオシアター [定員:240人]
開場
開会・主催者挨拶
オープニング上映『高崎での話』
(1951/20分/RKOパテ社)国立映画アーカイブ所蔵
戦後の占領下にあった昭和25年4月、連合国軍総司令部(GHQ)新聞課長が高崎で講演し、民主主義と地域社会の発展には郷土新聞の発行が欠かせないと説いた。これをきっかけに高崎市民は、株主100人、資本金20万円の株式会社を設立。「高崎市民新聞」が創刊された。週刊新聞として、市民生活に密着した記事を掲載した同紙は好評を博し、GHQは同紙を全国的な成功例として賞賛、映画『高崎での話』を制作した。昭和26年高崎電気館で上映されたときには大勢の市民がつめかけた。
[解説]
とちぎあきら(フィルム・アーキビスト/コミュニティシネマセンター理事)
プレゼンテーション+ディスカッションⅠ
アートとまちづくりの現在
高崎映画祭に始まり、映画館「シネマテークたかさき」に対する支援、「高崎電気館」の再開・運営、たかさきフィルムコミッションの運営など、高崎市は、映画や音楽等のアート・文化をまちづくりの主軸として、文化芸術活動を振興・支援してきました。今年の会場である「高崎芸術劇場」はその拠点となる重要な場所です。このセッションでは、福島や石巻といった東日本大震災の被災地で行われている最前線の事例をもとに、“まちづくりとアート”の可能性を探ります。
[登壇者]
橘豊[音楽・映画プロデューサー/高崎芸術劇場アドバイザー]
アメリカを始め、スイス、ブラジル、インド、フランス等、幅広く共同制作に携わる。2019年にはシンガポール、フランス、日本との合作映画『家族のレシピ』をプロデュース。全世界40ヶ国で配給され、フランスでは10万人以上を動員するヒットとなった。HBO Asiaのテレビシリーズ「Folklore」「Foodlore」の日本側プロデューサーとして、松田聖子の初監督作品、斎藤工監督作品をプロデュース。『家族のレシピ』を高崎で撮影したのが縁で、以降も高崎での撮影や文化活動に関わり、2020年には高崎芸術劇場アドバイザーに就任した。
松村豪太[一般社団法人ISHINOMAKI2.0代表理事/リボーン・アート・フェスティバル実行委員会事務局長]
東日本大震災後の2011年春、石巻市で「世界で一番面白い街を作ろう」を合言葉に、市内外の有志とともにISHINOMAKI2.0を設立、以来、様々なプロジェクトを展開してきた。2017年には「Reborn-Art=人が生きる術」をキーワードに掲げて始まった、「アート」「音楽」「食」の総合芸術祭「リボーン・アート・フェスティバル」(RAF、実行委員長=小林武史)の実行委員会事務局長に就任、現在にいたる。
立木祥一郎[合同会社tecoLLC代表/コミュニティシネマセンター役員]
川崎市市民ミュージアムシネマテーク設立、青森県立美術館建設計画策定に学芸員として参画。2007年tecoLLC設立。市庁舎、博物館、商業施設等の建設計画や展示設計、商品開発等に関わる。2012~13年「文化な仕事創造事業」(内閣府)で南相馬市の大正築映画館をめぐるドキュメンタリー『ASAHIZA 人間はどこへ行く』を制作。今年度、「原子力被災地における映像・芸術文化支援事業」(経産省)で相双地区における映画・演劇・現代美術等のアーティストインレジデンスを軸としたハマカルアートプロジェクトにディレクターとして参画。福島県の新たな魅力創出を目指す。
プレゼンテーション+ディスカッションⅡ
再生する映画館!~映画館はみんなのもの~
2023年5月8日、新型コロナウィルス感染症が「第5類感染症」に位置付けられたことによって様々な制限が解除され、2020年から3年間続いたコロナ禍は、ひとまず終息しました。しかし、この3年間で映画館を取り巻く状況は大きく変化しました。入場者数がコロナ以前に回復しない現在、地域の映画館はさらなる苦難に直面しています。
このセッションでは、映画館が置かれている実状を具体的な数値等で確認するとともに、火災を乗り越えて今年12月に”奇跡の復活”再建を期す「小倉昭和館」や、他の映画館との差異化をはかるため、新しい試みを続けるシネマコンプレックス、配給と映画館の連携等々、多彩な事例を聞き、コロナ後の新しい映画館・上映者のあり方を、地域との連携、観客との新しい関係の構築、映画館のサブスクリプション、上映支援策等々のテーマを含めて話し合います。
[進行] 北條誠人[「ユーロスペース」支配人/コミュニティシネマセンター理事]
プレゼンテーションマラソン2023
たかさきコミュニティシネマ(高崎映画祭・シネマテークたかさき&高崎電気館・高崎フィルムコミッション)、スタジオ6.11、前橋シネマハウス、伊参スタジオ映画祭、邑の映画会
群馬県外から あまや座(茨城県那珂市)、310+1cinema project(茨城県水戸市)、「福島芸術文化推進室」(経済産業省)、「日韓映写技師ミーティング in 福岡」(福岡市総合図書館)
レセプション
会場:ホテルメトロポリタン高崎 [定員:150人]
2023年9月23日[土・祝日]
会場:高崎市役所会議室
分科会
①映画祭の現在 地域の「国際」映画祭を考える+ディスカッション[定員:50人]
[登壇者]
堀越謙三(新潟国際アニメーション映画祭実行委員会委員長)、山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター)ほか
[進行]
志尾睦子(高崎映画祭 プロデューサー)
②フリーディスカッション どうする映画館?![定員:50人]
3年間のコロナ禍を乗り越えた映画館ですが、観客数はコロナ前の10~20%減という状況が続く中で、様々な支援もなくなり、デジタルシネマ機の更新も待ったなしの状況、まさに「どうする!」と迫られる日々…が続きます。そんな思いを語り合い、共有できる「何か」を見出す分科会です。
[進行]
北條誠人、山崎紀子(シネ・ヌーヴォ支配人/コミュニティシネマセンター理事)ほか
③Fシネマ・プロジェクト:フィルムの可能性〜映画の魅力を知ってもらうための試み〜[定員:50人]
フィルムはモノとして触れることができるところがデジタルと決定的に異なっています。実際に見る、触る、そして原理を知ることで、映画への興味を広げることができる、フィルムは魅力的なツールでもあります。いくつかのフィルムワークショップや上映会を紹介、分科会参加者にも体験してもらいます。
[登壇者]
神田麻美(映写技師)、郷田真理子(フィルム技術者/川崎市市民ミュージアム学芸員)、松本圭二(福岡市総合図書館 文学・映像課映像管理員)ほか
全体会
全国コミュニティシネマ会議開催記念上映会
[上映作品]
高崎の映画(1)
「第16回国民文化祭・ぐんま2001 in たかさき」シンポジウム関連作品
「2001 映画と旅」(15分/黒沢清監督)
「新世界」(18分/阪本順治監督)
「すでに老いた彼女のすべてについては語らぬために」(51分/青山真治監督)
トークゲスト:阪本順治監督
高崎の映画(2)
『珈琲時光』(2004年/103分/侯孝賢監督) 35ミリフィルムでの上映!
この上映会は、フィルムでの上映環境を確保するための「Fシネマ・プロジェクト」の一環として実施します。
高崎の映画(3)
『家族のレシピ』(2017年/89分/エリック・クー監督)
全国コミュニティシネマ会議2023イン高崎
日程:2023年9月22日[金]・23日[土]
会場:高崎芸術劇場(群馬県高崎市)ほか
群馬県高崎市栄町9-1 tel.027-321-7300
JR「高崎駅」東口から徒歩5分
◎9月1日[金]より受付開始!
[会場参加]
https://cckaigi2023-takasaki.peatix.com
*会場参加を希望する方は、9月15日[金]までにお申込みください。
*定員になり次第締め切らせていただきます。
会議 1,500円
*参加費は、当日受付にて現金にてお支払いいただきます。
*コミュニティシネマセンター団体会員は1団体1名無料。
*9月22日、23日共に参加可。一部のみの参加も同じ。
レセプション 4,000円
映画上映 一般1,000円/高校生以下500円
*コミュニティシネマセンター団体会員は1団体1名無料。
*各回入替
◎申込に関するお問い合わせ
コミュニティシネマセンター
TEL: 050-3535-1573 Email: film@jc3.jp
◎アクセスに関するお問い合わせ
NPO法人たかさきコミュニティシネマ(シネマテークたかさき)
TEL: 027-325-1744
主催:一般社団法人コミュニティシネマセンター、NPO法人たかさきコミュニティシネマ
協賛:(公財)高崎財団 後援:高崎市
助成:文化庁文化芸術振興費補助金[舞台芸術等総合支援事業・次代の文化を創造する新進芸術家育成事業]
独立行政法人日本芸術文化振興会
これまでの全国コミュニティシネマ会議
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
2023年
9月22日(金)、23日(土) 高崎[会場:高崎芸術劇場]
– プレゼン+ディスカッションI :アートとまちづくりの現在
– プレゼン+ディスカッションII :再生する映画館~映画館はみんなのもの~
– プレゼンテーションマラソン2023
– 分科会1:映画祭の現在―地域の「国際」映画祭について考えよう!
– 分科会2:フリーディスカッション どうする映画館?!
– 分科会3:Fシネマ・プロジェクト!フィルムの可能性~映画の魅力を知ってもらうための試み~
– 全国コミュニティシネマ会議開催記念上映会:
「第16回国民文化祭・ぐんま2001 in たかさき」シンポジウム関連作品「2001 映画と旅」(15分/黒沢清監督)「新世界」(18分/阪本順治監督)「すでに老いた彼女のすべてについては語らぬために」(51分/青山真治監督)
『珈琲時光』(2004年/103分/侯孝賢監督)※[Fシネマ・プロジェクト]
『家族のレシピ』(2017年/89分/エリック・クー監督)
2022年
11月18日(金)、19日(土) 盛岡[会場:岩手県公会堂]*オンライン配信も実施
– プレゼン+ディスカッションI :”映画祭”の時代
– プレゼン+ディスカッションII :「上映活動支援」制度を実現するために
– プレゼンテーションマラソン2022
– 分科会1:本と映画がであう場所—図書館・まちの書店とコミュニティシネマ—
– 分科会2:映画館(ミニシアター)における「こどもと映画プログラム」-若年層の観客を開拓する
– 分科会3:「”シアター未満”・”シアター以上”」-まちに創造される新たな上映空間。
– 全国コミュニティシネマ会議開催記念 フィルム上映会[Fシネマ・プロジェクト]:『息子』(1991/監督:山田洋次/121分)・『ハゲタカ』(2009/監督:大友啓史/134分)
2021年
2月3日(木) [会場:ユーロライブ(東京・渋谷)]*オンライン配信も実施
– プレゼンテーション コロナ禍の中で始めました。
– ディスカッション:“持続可能” な映画館/コミュニティシネマ
– 『こころの通訳者たち What a Whonderful World』プレミア上映[ユニバーサル上映]
2020年
12月16日(水) [会場:ユーロライブ(東京・渋谷)]*オンライン配信も実施
– 報告 コロナ禍と映画上映 これまで・現在・これから
・国内の映画館・上映者
・海外のアートハウスの状況(アメリカ、フランス、韓国)
– ディスカッション SAVE the CINEMA!
2019年
9月6日(日)、7日(月) 埼玉[会場:SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ]
– プレゼン+ディスカッションI :日韓コミュニティシネマ会議
– プレゼン+ディスカッションII:上映者が作り手を育てる
– プレゼンテーションマラソン2019
– 分科会1:やっぱり、ここで映画をみたい―映画館をつくる/映画館を再生する
– 分科会2:映画館におけるデジタルシネマの今後と公共施設におけるデジタルシネマの導入を考える
– 分科会3:子どもと映画プログラム~若年層の観客を開拓する
2018年
9月28日(金)、29日(土) 山形[会場:山形グランドホテルほか]
– ディスカッション:映像文化創造都市の可能性-“映画”が都市を魅力的にする
– プレゼンテーション+ディスカッション:映画上映の現在と未来―映画配信時代の上映
– 分科会1:地域の映像アーカイブとその活用について
– 分科会2:Fシネマで行こう!フィルム上映を企画しよう!
– 分科会3:若年層の観客を開拓する―大学生・高校生と映画館
– 分科会4:劇場の運営効率化を現場レベルで考えよう!
– 分科会5:上映初心者のための分科会~上映会企画ワークショップ
2017年
9月8日(金)、9日(土) 横浜 [会場:横浜市開港記念会館]
– 講演 ヨーロッパの映画館の現在と未来
– レクチャー:“上映”を定義する(仮)―映写の資源と映画館文化―
– ディスカッション:“上映”とは何か。~多様化する「上映」を考える
– プレゼンテーションマラソン “映画都市・横浜!”を中心に
– トーク:映画の世界へ誘う、字幕という仕事
– ディスカッション:あしたの映画館のすがた―続・ミニシアターの20年
▷ コミュニティシネマ会議2017チラシ
2016年
9月30日(金)、10月1日(土) 高崎 [会場:高崎電気館]
– プレゼンテーション:高崎における“コミュニティシネマ”~高崎映画祭からシネマテークたかさき、高崎電気館へ
– ディスカッション:温故知新?~コミュニティシネマのこれまでとこれから
– 特別上映+トーク:『煙突と映画館 みやこシネマリーン閉館の記録(仮題ダイジェスト版)
– コミュニティシネマ“プレゼンテーション・マラソン!”
– ディスカッション:地域のミニシアターの20年
– トーク:「映画の本『ジャックと豆の木』創刊関連トーク“劇場と映画と観客を結ぶ”
– コミュニティシネマの映画“コミュニティシネマのシネマ”のススメ
▷ コミュニティシネマ会議2015チラシ
2015年
9月4日(金)、5日(土) 新潟 [会場:新潟県民会館小ホール/リュートピア 新潟市民芸術文化会館]
– 基調報告:文化創造都市・新潟と映画
– ディスカッション:文化政策の中の映画上映振興策
– プレゼンテーション:新潟のコミュニティシネマ
– ディスカッション:新しい映画上映のかたち~これから映画上映をはじめる人たちのために
– 分科会1:小さな町のコミュニティシネマ
– 分科会2:大きな町のコミュニティシネマ
▷ コミュニティシネマ会議2015チラシ
2014年
10月22日(水)、23日(木) 東京 [会場:東京国立近代美術館フィルムセンター]
スクリーン体験フォーエバー! ~私たちはスクリーンで映画をみたい/みせたい
– トーク:香川京子(女優) 「映画は大きなスクリーンでみてほしい」
– プレゼンテーション: 「スクリーン体験」をめぐる現状 / 新しい映画上映振興策について
– ディスカッション: 映画上映の現状と望ましい映画上映振興策 ~その実現に向けて
– 映画上映と解説: 「MoMAニューヨーク近代美術館映画コレクション」関連企画
– 『ニューヨークの地下鉄』 他 上映 解説: MoMAフィルムコレクションの魅力とFシネマ・プロジェクト
– コミュニティシネマのプレゼンテーション
– セッション1:コミュニティシネマとしての映画館(シネマ・シンジケート・プロジェクト)
– セッション2:Fシネマ・プロジェクト ~フィルムの上映環境を確保するために(シネマテーク・プロジェクト)
– セッション3:コミュニティの中の映画祭の可能性
▷ コミュニティシネマ会議2014チラシ
2013年
9月6日(金)、7日(土) 浜松市 [会場:クリエート浜松]
コミュニティシネマのリノベーション! ~映画を軸にクリエイティブなまちづくりを考える~
– ワークショップ: あなたの劇場の「デジタル化」の現状を話し合おう!
– ディスカッション: 映画館(コミュニティシネマ)のリノベーション!
– コミュニティシネマに関するプレゼンテーション
– 映画上映: 『楽隊のうさぎ』(監督:鈴木卓爾/2013年/97分) *プレミア上映
– 分科会1: 映画祭の現在―魅力的なプログラムのあり方
– 分科会2: Fシネマ・プロジェクト~フィルムの上映環境を確保するために
– 分科会3: シネマ・シンジケート・プロジェクトを検証する
– プレゼンテーション: 『楽隊のうさぎ』ができるまで
– ディスカッション: 映画をつくること/映画を上映すること/コミュニティをつくること
– ワークショップ: 作品に即した広報宣伝戦略とは ~『楽隊のうさぎ』をモデルケースに~
▷ コミュニティシネマ会議2013チラシ
2012年
9月8日(土)、9日(日) 那覇市 [会場:桜坂劇場]
魅力的なまち、居心地のいい場所≒コミュニティシネマ
– プレゼンテーション: 魅力的なまち・那覇をかたちづくる人たち ~桜坂劇場のまわりにいる人たち~
– ディスカッション: 居心地のよい場所≒コミュニティシネマ ~桜坂劇場 大解剖!~
– 報告: 「シネマエール東北 東北に映画を届けよう!プロジェクト」 レポート
– ディスカッション: 残す? 残さない? -35ミリ上映環境の確保について考える
– 映画上映: 『ビラルの世界』(監督:ソーラヴ・サーランギ/2008年/88分) *コミュニティシネマ賞授賞作品
– ディスカッション: 高校生の映画館 イン 桜坂
▷ コミュニティシネマ会議2012チラシ
2011年
9月2日(金)、3日(土) 広島市 [会場:広島市映像文化ライブラリー他]
シネマエール東北 ~映画の可能性を信じて
– 基調報告: 映画応援団―シネマエール東北 東北に映画を届けよう!プロジェクト
– ディスカッション: 映画に何ができるのか
– コミュニティシネマに関するプレゼンテーション
– 映画上映: 『広島・長崎における原子爆弾の影響』 (1946年/164分) *部分上映
– 講義: ヨーロッパにおける映画教育の現在
– 報告とディスカッション: 高校生のための映画館(仮)プロジェクトの実施について
– 映画上映:
『ボクシング・ジム』(監督:フレデリック・ワイズマン/2010) *日本初上映
『ニュース映画に見るヒロシマ、ナガサキ、ビキニ』
『二十万の亡霊 200000 Phantoms』(監督:ジャン・ガブリエル・ペリオ/2007)
▷ コミュニティシネマ会議2011チラシ
2010年
9月10日(金)、11日(土) 山口市 [会場:山口情報芸術センター(YCAM)]
“メディア芸術センター”としてのコミュニティシネマの可能性
– 基調報告: メディア芸術センターとしてのコミュニティシネマ
– 基調報告Ⅰ: 山口情報芸術センターの中の“映像”
– 基調報告Ⅱ: コミュニティシネマの未来系 “映像メディアセンター”プラン
– プラン1: 弘前市吉井酒造煉瓦倉庫アートメディアセンター構想
– プラン2: 「空想のメディア芸術センター」構想
– ディスカッション: “メディア芸術センター”としてのコミュニティシネマの可能性
– 新しいコミュニティシネマに関するプレゼンテーション
– 名画座フォーラム: 日本映画クラシック作品の上映環境を考える
– 講義: デジタルシネマの現在
– 映画上映:
『海炭市叙景』(監督:熊切和嘉/2010) *シネマ・シンジケート作品
『トラス・オス・モンテス』(監督:アントニオ・レイス/1976) *シネマテーク・プロジェクト作品
▷ コミュニティシネマ会議2010チラシ
2009年
9月4日(金)、5日(土) 川崎市 [会場:川崎市アートセンター ほか]
政策の中の映画
– 基調講演:岡島尚志(東京国立近代美術館フィルムセンター主幹/国際フィルム・アーカイヴ連盟会長)
「フィルム・アーカイヴと映画上映の未来」
– プレゼンテーション: 映画館と映像のまちづくり
– ディスカッション: 政策の中の映画
– 分科会1: 映画祭/シネクラブ~地域における映画祭を考える~アジア映画の魅力
– 分科会2: シネマテーク・プロジェクト+映像教育部
– 分科会3: シネマ・シンジケート~ 映画館における“アウトリーチ”を考える
– 映画上映:
『オルエットの方へ』(監督:ジャック・ロジェ/1969年/154分)
– 「生誕百年記念 映画監督 山中貞雄」シンポジウム(シネマテーク・プロジェクト関連企画)
シンポジウム:
青山真治(映画監督/小説家)、西山洋市(映画監督)、
廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)、クリス・フジワラ(映画批評家)
上映作品:『河内山宗俊』(監督:山中貞雄/1936年/81分)
▷ コミュニティシネマ会議2009チラシ
2008年
8月29日(金)、8月30日(土) 仙台市 [会場;せんだいメディアテーク]
都市に映画の文脈(コンテクスト)を育む
– 基調講演: ワン・パイジャン(「台北之家」プログラム・ディレクター)
「台湾のコミュニティシネマ “台北之家”について」
– プレゼンテーションとディスカッション: 都市に映画の文脈(コンテクスト)を育む
– 分科会1: シネマテーク・プロジェクト
– 分科会2: シネマ・シンジケート
– 分科会3: 映画祭/シネクラブ
– 分科会4: 映像学芸員 ―資格の新設とその目的
– 分科会5: 子どものための映画映像教育
– 映画上映:
『秉愛』(監督:馮艶(フォン・イェン)/2007) *監督舞台挨拶
『シャーリーの転落人生』(監督:冨永昌敬/2008)
『罪の天使たち』(監督:ロベール・ブレッソン/1943)
▷ コミュニティシネマ会議2008チラシ
2007年
8月31日(金)、9月1日(土) 東京 [会場:東京国立近代美術館フィルムセンター]
映画を伝達する ~批評、メディア、観客
– 基調講演:蓮實重彦(映画批評家/東京大学元総長)
「『モンゴメリー・クリフ(ト)問題』について―映画史のカノン化は可能か?」
– ディスカッション1: 映画を伝達する─批評、メディア、観客
– ディスカッション2: 上映システムを強化する
– 分科会1: アートシネマ・シンジケート(仮称)構想
– 分科会2: シネマテーク・プロジェクト構想
– 映画上映:
『煙り草物語』(1924)、『斬人斬馬剣』(1929)、『石川五右衛門の法事』(1930)、『國士無双』(1932)、
『RHYTHM [リズム]』(1935)『百年後の或る日』(1933)
– コミュニティシネマのプレゼンテーション
▷ コミュニティシネマ会議2007チラシ
2006年
9月8日(金)、9日(土) 札幌市 [主催:NPO法人北海道コミュニティシネマ・札幌]
デジタル時代の映画上映 ~上映することの意味を考える
– 基調講演: 中谷健太郎(由布院「亀の井別荘」主人) 「ソコが、ココになる日~由布院盆地は再生するか?」
– プレゼンテーションとディスカッション: デジタル時代の映画上映
– 分科会1: 映画教育について考える ~学校と映画の関係
– 分科会2: デジタル上映とは何か ~デジタルシネマの世界的動向から日々の上映まで
– コミュニティシネマに関するプレゼンテーション
– 映画上映: 『壁男』(監督:早川渉/2006年/98分) *プレミア上映
▷ コミュニティシネマ会議2006チラシ
2005年
11月11日(金)、12日(土) 金沢市 [会場:金沢市文化ホール、金沢21世紀美術館]
芸術の創造力がまちを再生する -映画とまちの関係を考える –
– 基調講演:ジャン=ルイ・ボナン(フランス・ナント市文化局長) 「文化でよみがえるフランスの都市ナント」
– プレゼンテーション:
公設民営映像ホールの実現に向けて (KAWASAKIしんゆり映画祭)
金沢コミュニティシネマ構想 (金沢コミュニティシネマ推進委員会)
– ディスカッションⅠ: 芸術の創造力がまちを再生する――映画とまちの関係を考える
– プレゼンテーション:
アーティストと子どもたちの出会い ~ASIASの試み
フィルム・アーカイヴによる映画教育プログラムの可能性
– ディスカッションⅡ: 子どもたちと映画 ~映画上映と教育プログラム
– コミュニティシネマに関するフリーディスカッション
– 映画上映: アピチャッポン・ウィーラセタクン監督作品
『トロピカル・マラディー』(2004)、『アイアン・プッシーの大冒険』(2003)、
『ブリスフリー・ユワーズ』(2002)、『真昼の不思議の物体』(2000)
▷ コミュニティシネマ会議2005チラシ
2004年
8月20日(金)、21日(土) 高知市 [会場:高知県立美術館]
映画教育について考える
– 基調講演1: アラン・ベルガラ(パリ第三大学映画教授、映画作家・研究者)
「フランスにおける映画教育」
– 基調講演2: ウェンディ・アール(英国映画協会BFI教育部門リソース・エディター)
「イギリスにおける映画教育の実践」
– ディスカッション:映画教育を考える
– 映画教育に関するプレゼンテーションⅠ:高知における教育プログラムの事例報告
– 映画教育に関するプレゼンテーションⅡ:国内の映画教育実践報告
– アラン・ベルガラ氏によるワークショップ
– コミュニティシネマに関するフリーディスカッション
– ワークショップと映画の上映: のぞいてみようよ 映画の国 『菊次郎の夏』(監督:北野武/1999年/121分)
▷ コミュニティシネマ会議2004チラシ
2003年以前の会議
映画上映ネットワーク会議2003イン大阪 (9月 大阪市)
“コミュニティシネマ”宣言!
映画上映者ネットワーク会議2002 (9月 岐阜市)
地域における映画環境の変化と“コミュニティシネマ”(公共映画館)の可能性
基調講演: ポク・ファンモ(韓国湖南大学演劇映像学科助教授) 「韓国の映画振興制度」
映画上映者ネットワーク会議2001 (11月 東京)
日本における映画文化の振興を考える 地域の活性化(まちづくり、都市計画)と映画
映画上映者ネットワーク会議2000 (11月 高崎市)
地域の活性化・映画の活性化
基調講演: デビー・シルバーファイン(ニューヨーク州芸術評議会副理事、電子メディア・映画部門ディレクター)
「ニューヨーク文化はいかにしてつくられるか」
映画上映者ネットワーク会議1999 (9月 青森市)
地域における映画・映像上映・創造の拠点づくり~地域を結ぶネットワークの将来像~
基調講演: カレン・アレクサンダー(英国映画協会BFIマーケティング部門責任者)
「英国における公共上映の状況――BFIの活動を中心に」
映画上映者ネットワーク会議1998 (9月 山形市)
公共上映の諸問題――日々の上映活動を考える
基調講演: マーク・ノーネス(ミシガン大学助教授)
「アメリカにおける公共上映の状況――ミシガン州アン・アーバー」
映画上映者ネットワーク会議1997 (8月 萩市)
地域の映画祭・映画上映を考える
基調講演1: ペーター・ベア(マンハイム・コミュナール・キノ「シネマクアドラ」)
「ドイツの都市・地方自治体における文化事業としての映画の上映活動について」
基調講演2: マリー=クリスチーヌ・ド・ナヴァセル(東京日仏学院院長、当時)
「フランスにおける映画とオーディオ・ヴィジュアル作品」
映画上映ネットワーク会議1996 (7月 福岡市)
地域の映画祭・映画上映を考える
基調講演: 高野悦子(岩波ホール総支配人) 「映画がつくる文化交流」

